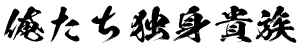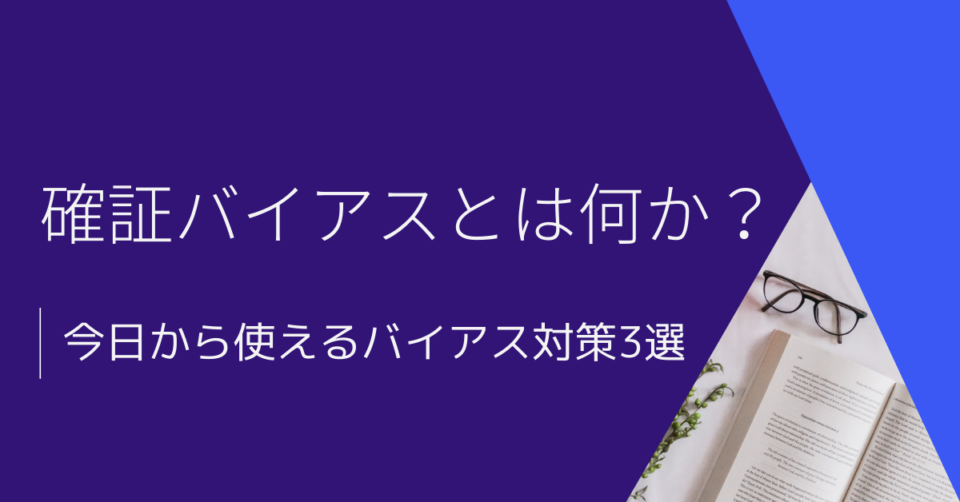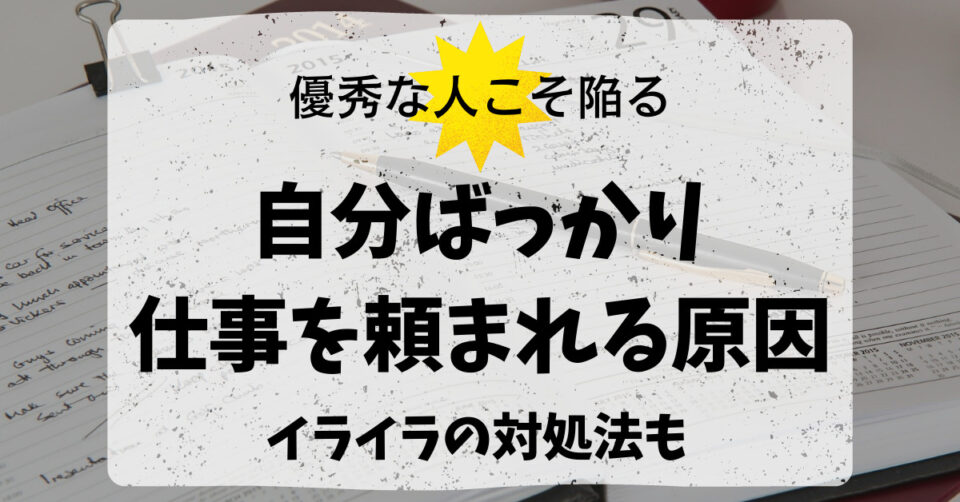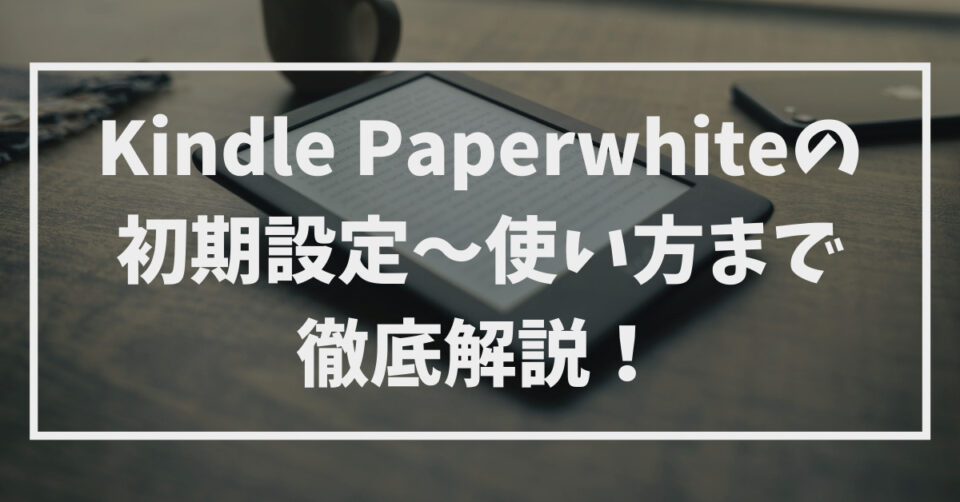こんにちは、生涯独身男のSoutaです。

具体的に生活にどう関係しているの?対策も知りたい!
そう思っている方には参考になる記事です。
この記事を読めばコレがわかる!
- 確証バイアスとは?
- 確証バイアスの実例と対策法
▼自分ばかりに仕事を押し付けられて悩んでいる方へ。
-
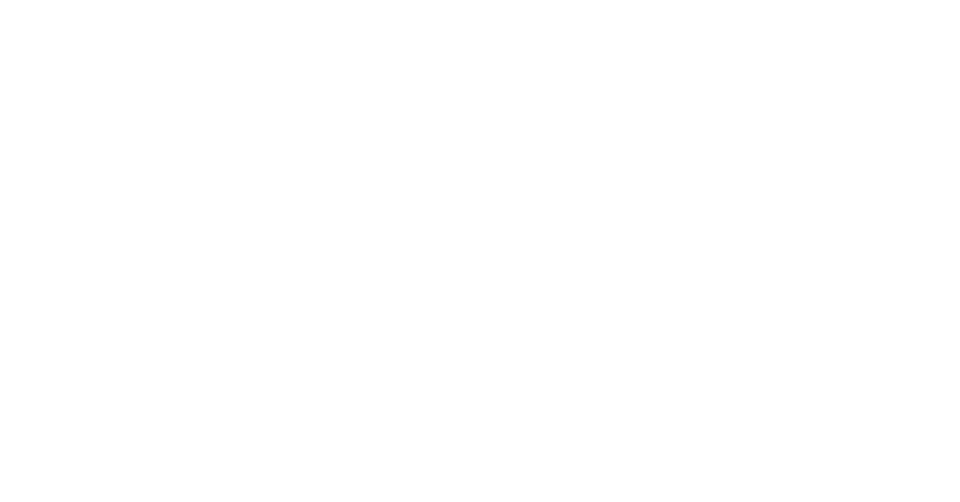
自分だけ仕事を頼まれてイライラ…気持ちを落ち着かせる考え方をご紹介
続きを見る
▼読書は電子書籍の時代へ。Kindleが便利です。
-
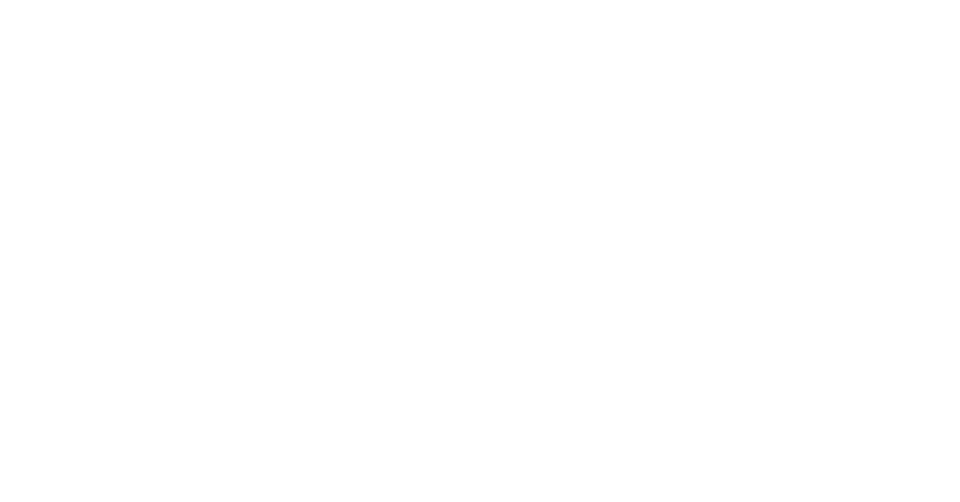
Kindle Paperwhiteの初期設定から使い方まで徹底解説!はじめての方も安心して使えます
続きを見る
Contents
確証バイアスとは?
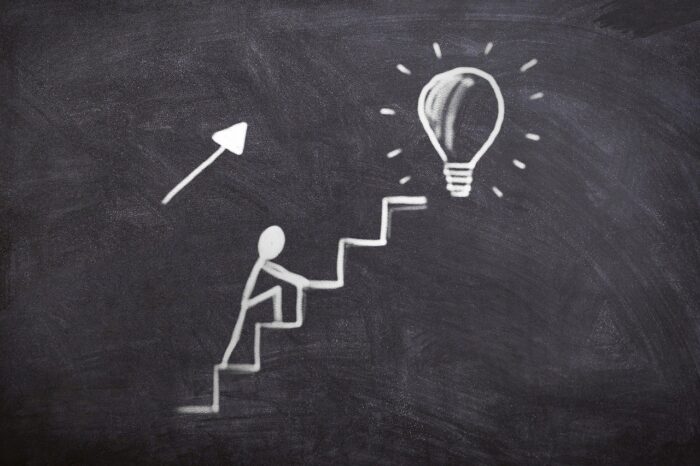
確証バイアスとは、自分が正しいと考えていることを確証してくれる情報に注意を向けがちになってしまうことを言います。
ここで、確証バイアスが表われる有名な実験をご紹介します。
「2-4-6課題」と呼ばれる実験です。知っている方もいるかもしれません。
2-4-6課題
ここに「2,4,6」と3つの数字からなる数列があります。
この数列は「とあるルール」に基づいた数列です。
あなたの目標はこのルールを見つけることです。
実験手順はこの通りです。
実験手順
- あなたは、自分で新たな数列を作成し実験者に提示します
- 実験者は、あなたが作った数列がルールに当てはまるか、否か?「yes/no」で回答します
- 上記を繰り返して、数列のルールがわかり次第、実験者に報告します
といったものです。
おもしろいのはこの実験の結果なんです。
この実験のほとんどの参加者は以下の通りの結果となったそうです。
実験結果
参加者は「8,10,12」や、「20,22,24」といった数列を実験者に提示したところ、
「yes」(つまりルールに当てはまる)と回答されました。
そこから大多数の参加者は「連続した2の倍数の数列」がルールだと結論付け実験者に報告しました。
しかし、実験者から「違う」(そのルールではない)と言われてしまいました。
ちなみに正解のルールは単なる「上昇系列」。
つまり「前の数よりも大きい数字の数列」が答えだったそうです。
実験者の心理から確証バイアスを紐解く
実験者たちの大半は、「2,4,6」という数列を見た時に、
「連続した2の倍数ではないか?」という仮説を立てました。
つまりその仮説が正しいかを検証するために「8,10,12」などの数列を提示しました。
そしてその回答が「yes」。実験者は仮説が正しかったと信じ、もう疑いません。
これが確証バイアスです。
自分の仮説を証明するために「8,10,12」という自分に都合の良い数列だけを作ったのです。
ちなみに「2,4,6」の数列は他にも多数のルールが考えられたはずです。
- 2個ずつ増える数列(1,3,5など)
- 3つ目の数字が前2つの和になっている数列(9,5,14など)
- 単に偶数の数列(2,456,100など)
ですから「連続した2の倍数の数列」であると確かめるためには、
上記に出てきた仮説を潰す数列を作成しなければいけません。(反証と言います)
しかしそれを行う参加者は少なかったそうです。
以上が実験の内容です。
確証バイアスの実例
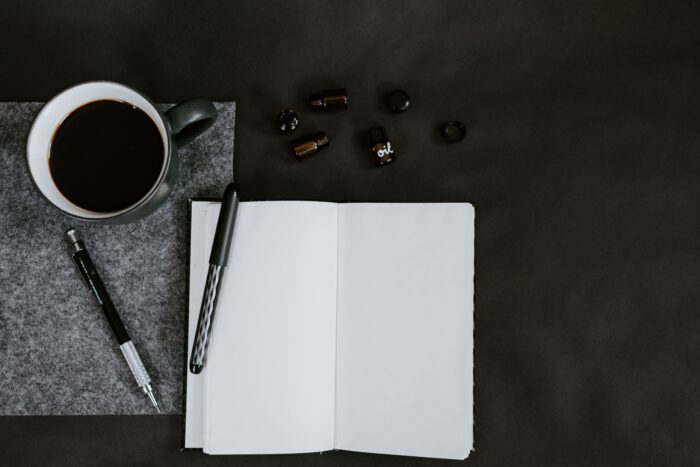
先ほどの実験で、確証バイアスへの理解が深まったかと思います。
続いて日常で確証バイアスが使われる実例をご紹介します。
第一印象
「第一印象が大切」という話を聞いたことがあると思います。
この話は確証バイアスを用いて説明すると納得がいきます。
確証バイアスが働くことを考えると、一度その人を立派な人だと思うと、その後はその人が立派であるという情報のみに注意が向くはずです。
逆に「だらしない」という印象を感じても、
「今日は疲れているのかな?」と感じその人への評価が下がることは少ないです。
これも前提に確証バイアスがあるからこそですね。

血液型と性格
血液型占いなどがあるように、血液型と性格には関係があると思っている人がいます。
こういうたとえを聞いたことがないでしょうか?
血液型占いの例
- A型:几帳面
- B型:わがまま
- O型:おおらか
- AB型:センスが良い

筆者含めたB型は肩身の狭い思いをします。
「血液型と性格は本当に関係があるか?」という真偽は割愛しますが、
このたとえを持ち出して、
やっぱりB型の人ってわがままだよ。

などという話を一度は耳にしたことがありませんか?
そう、これが確証バイアスに支配された例です。
「B型はわがままである」という仮説を証明するため、適合例だけが持ち出されます。
はたして「几帳面なB型」や「おおらかなB型」や「センスが良いB型」は存在しないのでしょうか?考えるまでもありません。
しかしみんなそこには目を向けません。これが確証バイアスです。
確証バイアスの対策法3選

続いて確証バイアスの対策をご紹介します。
- バイアスは誰もが持っていることを自覚する
- 客観的な視点を持つ
- クリティカルシンキングで物事を考える
順に解説します。
バイアスは誰もが持っていることを自覚する
今回ご紹介している確証バイアスは、
仕事でも恋愛でも役立つことですが、知っている人は少ないです。

と自覚できなければ、その対策も打ちようがないのです。
ですからまずはここから意識しましょう。
この記事を読んで頂いているあなたも、あなたの友達や家族も、もちろん私も。
誰しもが何かしらのバイアス(思い込み)を持っています。
「自分は今バイアス(思い込み)にかかっていないか?」と立ち止まることが大切です。
トヨタ生産方式で有名な「なぜなぜ分析」のように、
「そう判断したのはなぜか?」と自問して、思い込みのみで判断していないかを確認しましょう。
客観的な視点を持つ
主観のみで物事を判断するのではなく、時には客観的な視点を持つようにしましょう。
ここでいう客観的な視点とは具体的に以下のようなことです。
客観的な視点とは
- 第三者に意見を求めること
- 統計などの数字やデータを見ること
確証バイアスにかかっている状態で、自分の考えを変えることは難しいです。
ですからこのように客観的な視点を持つ事を大切にしましょう。

自分を律する良いきっかけになります。
クリティカルシンキングで物事を考える
クリティカルシンキングとは日本語で「批判的思考」と呼ばれるものです。
もう少し具体的に説明すれば、
「物事を鵜呑みにせず、自分の考えの前提を崩して新しい視点を得る」力のことです。
「批判」という言葉が入っていますが、
新しい視点を得ることが目的であって、「批判」が目的ではないので注意しましょう。

確証バイアスから抜け出そうというわけです。
クリティカルシンキングは先ほど紹介したように第三者の意見も不要で、基本的には1人でできます。
慣れてくると結構楽しくて、新しい仮説が生まれたり中々おもしろいです。
とくに仕事などには応用が利くと思うので、ぜひ試してみてください。
私がクリティカルシンキングをする時は、
わざと下記のような自問をしています。
- いや、でもそれって~~~ではないだろうか?
- それが目的ならば、~~~が代わりになるのではないか?
- なぜ~~~ではダメなのだろうか?
- もし~~~のような問題が発生しても、このままでよいのだろうか?
こういった自問をすることで、「なぜ自分が今それをやっているのか?」
具体的な根拠を持って行動できます。

「我、天啓を得たり」という気分になります。
人間は必ずバイアスを持っている
先ほど書いたようにバイアスは誰しもが持っているものです。
最近ではバイアスという言葉も一般的に用いられるようになりました。
ですからよく「バイアスを持つ事=悪いこと」と誤解されますが、そうではありません。
バイアス(思い込み)によって不合理な選択を招く可能性がある反面、
バイアス(思い込み)があったからここまで人類は発展を遂げることができたとも言えます。

ということですね。
ですから私たちはバイアスの存在を認識し正しくコントロールしなければなりません。
今日ご紹介した確証バイアスは数あるバイアスの中の1つです。
まずは確証バイアスを正しく理解してコントロールできるようにしましょう!
まとめ

今回は、確証バイアスとはなにか?そして確証バイアスの対策について解説しました。

まずはそれを認識する事が大切です。
最後にもう一度この記事の要点を振り返ります。
確証バイアスとは
- 自分が正しいと考えたことを確証してくれる情報に注意を向けがちになること
確証バイアスの対策
- バイアスは誰もが持っていることを自覚する
- 客観的な視点を持つ
- クリティカルシンキングで物事を考える
▼バイアスについてもっと知りたい方はコチラの本がオススメ
この記事を読んだ方が少しでも参考になれば嬉しいです。
今回は以上です、それでは!